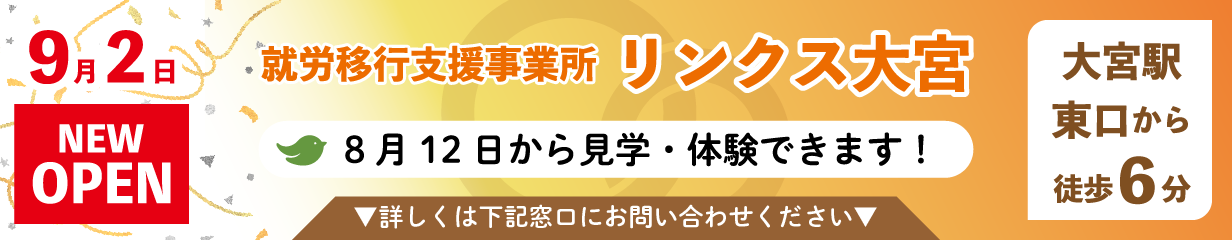第2回ストレスコントロール【心理学講座】

金曜日の4コマ目は毎週恒例の講座の日!(^^)!
今回で2回目なので、講座の冒頭では前回の振り返りからスタートしました。
「ストレスや、それを感じた時の状態」に対する一般的なイメージを
参加された方にお聞きしたところ、
・重たいもの
・頭が締め付けられる
・息が苦しくなる
・心が空っぽになる
等の意見が挙がり、これらの意見からもなんとなくマイナスのイメージを持っている方が多いという事が分かります。
ストレスは本当に人をイライラさせるだけなのでしょうか?
今回の講座では、実はマイナスの面だけではないという、
ストレスを感じた時の反応について紹介しました。

ストレスを感じるとイライラしたり、不安に駆られてドキドキする等という経験は誰にでもあり、
イメージが付きやすいのではないかと思いますが、
ストレスを感じると体の中ではそれに対処するために様々な反応が生じます。
以下に、最近の研究で分かってきた3つのストレス反応について紹介します!
【闘争・逃走反応:体中の力と意思力を集結させる】
警戒態勢を取って瞬時に行動出来る様、交感神経の働きによって体全体のエネルギーを集結させます。
生命の危険を感じる様な危機的な状況に陥った時、普段の自分では信じられないような力が出た
といったような事はニュース等で耳にしたことがあるのではないかと思います。
いわゆる「火事場の馬鹿力」というのがこの反応が起きている状態と言えます。
ストレスによって生じるエネルギーは、行動を促すだけでなく、
脳を活性化して重要でない事は意識から外すなど情報を急速に処理します。
このように、ストレスには注意力を高め、意識を集中させる働きがあるのです。
【チャレンジ反応:最高のパフォーマンスを引き出す】
ストレスがあってもそれほど危険で無い場合には、アドレナリンが急増して
筋肉と脳にはエネルギーがどんどん送り込まれ、気分を高揚させる化学物質が急増します。
この反応が起こると集中力は高まるが、恐怖は感じていない状態であるため、
プレッシャーのかかる状況でもやるべきことをやれるようになるのです。
【思いやり・絆反応:社会的なつながりを強化する】
ストレスを感じた時、誰かに話したくなったり会いたくなったりといった経験はありませんか?
これもストレス反応の一種で、ストレスを感じると多くの場合、
人とのつながりを求める気持ちが強くなるそうです。
これはオキシトシンと呼ばれるホルモンの影響で、
このホルモンが脳に及ぼす影響として周囲の人の考えていることや感情に気付き、
理解する力が強まるそうです。
あなたが友人や大切な人の声を聞きたくてたまらない時は、
ストレス反応が起こって、助けを求めようとしているのかもしれません。
これは生理学的な反応で、「自分を守りたい」「誰かを守りたい」という、
向社会的なストレス反応なのです。
ストレスと聞くと、なんとなく「悪い」イメージを持っている方が多いですが、
実はその裏にこのようなプラスの面もあったのですね(^^♪

このようにストレスを感じた時の反応には様々な物がありますが、
どういう反応を起こすかはどんな状況でストレスを感じるかによって変わってきます。
また、これまでの人生で経験してきた出来事も、
ストレスへの反応のしかたに影響を及ぼす可能性があるのではないかと言われています。
ただ、ストレスを感じた時、体は生物学的に経験から学びやすい状態になっているため、
ストレス反応には計画的な訓練の効果が極めて現れやすいと言われています。
言い換えると、ストレスに対する体の反応はあなたが望むように変えることができるという事です。
ストレスを感じた時にどんな行動を取ろうと、
脳と体はそれを覚え、自動的に同じ行動を取るようになるそうです。
これらのことから、これまでの習慣を変えるために、
ストレスを感じた時に「新しい反応のしかた」を練習して試してみるのも良いかもしれません(^^♪